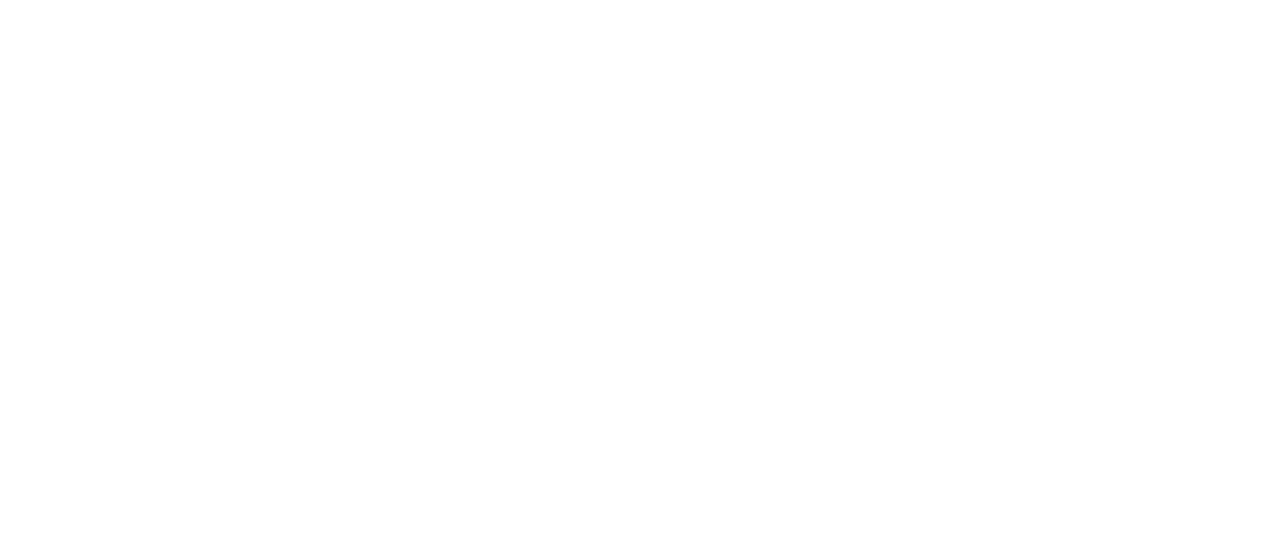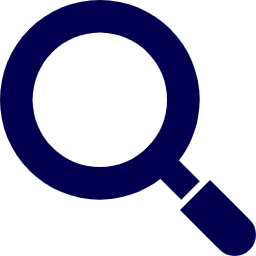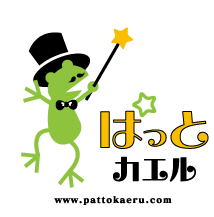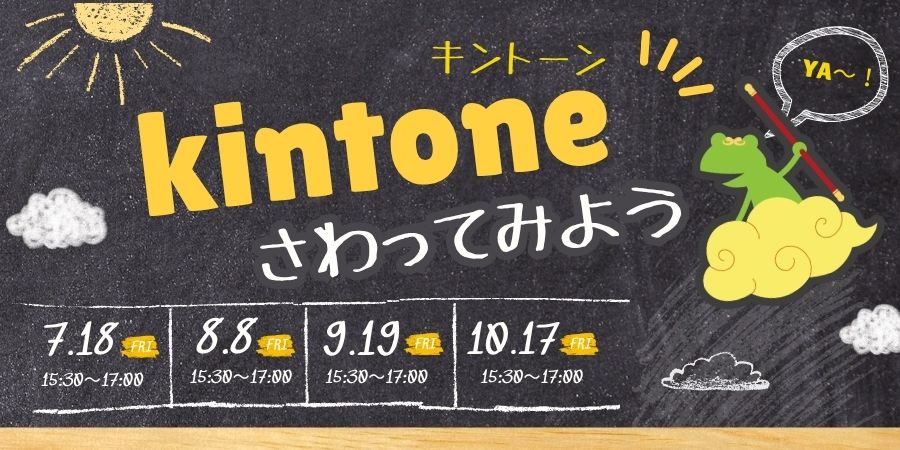RPA導入で得する仕事、損する仕事
2025.04.03
1.RPAって結局、何ができるの?
1.1 ざっくり理解!RPAの基本機能
RPAという言葉はよく耳にするけれど、「実際に何ができるのかはピンとこない」という声、よく聞きます。RPA(Robotic Process Automation)は、ざっくり言えば「人間がパソコン上で繰り返し行っている作業を自動でこなすロボット」です。
たとえば以下のような作業、全部RPAで代替できます。
- 毎朝の売上データの集計とメール送信
- 請求書のPDFをメールから保存し、クラウドに格納
- 顧客情報をExcelから社内システムに転記
- 定型のメール返信(問い合わせ対応など)
これらはすべて「決まった手順で、同じ操作を繰り返す」作業。人間がやると時間がかかり、ミスも出やすい。それを24時間365日、ミスなく淡々とこなすのがRPAの得意技なんです。「プログラムを組まないといけないんじゃないの?」と思われがちですが、近年はノーコード(プログラミング不要)で作れるRPAツールが増えており、ITに詳しくなくても使いこなせるレベルになってきています。
1.2 自動化に向いている仕事の特徴とは
とはいえ、何でもかんでもRPAで自動化できるわけではありません。導入効果を最大化するには、「向いている仕事」と「向いてない仕事」を見極めるのが大事。
RPAに向いている仕事には、以下のような共通点があります。
- ルールが明確:例外が少なく、毎回の処理手順が同じ
- 繰り返しが多い:毎日、毎週など頻繁に行われる
- 大量処理がある:データ件数や処理量が多い
- デジタルで完結している:紙や電話が絡まず、PC上だけで完結
たとえば「Excelで請求データを整理し、PDFで出力して、社内システムに登録する」といった一連の業務。これは条件さえ決まっていれば、丸ごとRPAに任せることができます。
逆に、「複雑な判断が必要」「人との会話がある」「毎回内容が違う」といった作業は、まだRPAには難しいところ。
この後ご紹介する「RPA導入で得する仕事10選」では、こうした「向いている仕事」の中でも、特に効果が高いものをピックアップしています。
1.3 RPAツールの種類と選び方のポイント
ここまでで、「RPAがどういう作業をこなせるのか」「どんな業務が向いているのか」が見えてきたと思います。
では実際に自社に導入する際、「どのようなツールを選ぶべきか?」という視点も重要になってきます。
RPAツールには大きく3つのタイプがあり、それぞれ得意な作業や制約があります。
- デスクトップ型:個人のPCにインストールして使用。比較的低コストで始められるが、PCが起動している間しか動作しない
- サーバー型:社内サーバーで稼働。複数の業務を24時間自動実行できるが、初期コストとメンテナンスコストがかかる
- クラウド型:インターネット経由でサービス提供。導入が容易でスケーラブルだが、機密性の高いデータ処理には向かない場合も
選定のポイントは以下の4つ:
- 使いやすさ:技術スキルが高くない社員でも使える直感的なインターフェースか
- サポート体制:日本語でのサポートが充実しているか、問い合わせ対応は迅速か
- 価格体系:初期費用と運用コストのバランスが適切か、ROIは見込めるか
- 拡張性:将来的な業務拡大に対応できる柔軟性があるか
最初は小規模なプロジェクトから始めて、実績を積みながら徐々に拡大していくのが賢明なアプローチです。
2. RPA導入で得する仕事10選
ここでは以下の3つの視点から、「RPA導入で得をしやすい仕事」を評価しています。
- 作業時間の短縮度:どれだけの時間をRPAで削減できるか
- ヒューマンエラーの削減度:人間がやると起こりがちなミスの回避レベル
- 業務頻度・量:繰り返しの多さ、または処理件数の多さによる効果範囲の広さ
これらをベースに、実際の導入事例・現場の声・業務内容などを加味して順位付けしています。
2.1 意外と効く業務たち
1:在庫管理表の更新
定期的にデータを入力・集計する在庫表は、ルールが明確でRPAと相性良し。「最新データを別システムから取り込む→表を更新→ファイルを保存」の流れが定番パターン。自動化により入力ミスもゼロに。
2:郵送物の発送リスト作成
宛名リストや発送履歴を毎月Excelで整える…この地味な作業もRPAなら高速処理。印刷ソフト連携やラベル出力まで自動化している企業も。
3:営業アポ状況の集計と共有
営業マンの入力ミスや遅れでぐちゃぐちゃになりがちなアポ進捗表。RPAなら入力チェック+データ収集+レポート作成まで一気にこなして、管理コスト大幅減。
4:勤怠データの集計
勤怠システムからデータを取り出してExcelにまとめる作業は、RPAで鉄板の自動化ネタ。複数拠点や部署がある会社ほど効果絶大。
5:取引先への一括請求メール送信
PDF添付して、定型文でメール送って、履歴を残す。手動だとミスが出やすく、時間もかかるが、RPAなら毎月同じタイミングで自動送信可能。法務や会計にも好評なRPA業務。
2.2 効果絶大な仕事ベスト5
6:経費精算のチェックと入力
社員から提出された経費精算書の金額・内容を確認し、システムに入力する…この地味だけど重要な業務、意外と時間がかかります。特に人数が多い企業では「確認・入力だけで半日潰れる」なんてことも。
RPAであれば、添付されたデータから必要な情報を抽出し、会計ソフトに自動入力。ミスもなく、月末の処理負担が劇的に軽減されます。
7:受注データの入力と処理
ECサイトや営業部門から届く受注情報を、販売管理システムに手入力している会社、まだまだ多いです。この工程、実はRPAとの相性バツグン。
注文内容の自動確認 → システム登録 → 顧客への確認メール送信まで、全部RPAで自動化可能。受注量が増えても人的リソースを増やす必要なし!
8:請求書の発行・送付業務
毎月決まったタイミングで大量の請求書を発行し、PDF化して、顧客ごとに送信…。この定型業務、RPA導入でのROI(投資対効果)が非常に高い分野です。
RPAなら、金額チェックからファイル生成、メール送信、さらには控えの保存まで一括処理。法務・会計部門からの「もう戻れない」との声、多数。
9:売上・在庫レポートの自動作成
「毎週月曜日に、先週の売上と在庫推移をまとめて報告」このレポート作成に2時間かけているとしたら、年間で100時間以上が無駄に。
RPAは複数のシステム・ファイルから必要なデータを抽出・整形し、グラフ化してレポートにまとめるのが得意中の得意。精度も安定しており、上司のチェックも一発OK。
10:データの転記・コピー作業
栄えある第1位は…やっぱり「転記作業」。社内システムやExcel、Webサイト間でのコピー&ペースト。これ、すべてRPAが一番得意なジャンルです。
しかもこの作業、ほとんどの職場で毎日のように行われている。言い換えれば、「誰でも即、効果を実感できるRPA業務」です。
情報の間違いも起きにくくなり、作業者のストレスも激減。一度導入すれば「もう手作業に戻れない」と感じる代表格です。
3. RPA導入で損する?向いていない仕事の共通点
3.1 RPAが不得意な業務とは?
RPAはとても便利ですが、万能ではありません。導入すればすべてが解決するわけではなく、向いていない仕事に使うと「効果ゼロ」どころか、逆に手間が増えることすらあります。では、どんな業務がRPAに不向きなのか?代表的な特徴は以下の通りです。
- 作業内容が毎回違う:判断が必要だったり、手順がバラバラな作業はRPAが苦手
- 紙が中心の業務:紙資料の読み取りにはAI-OCRなどの追加技術が必要になり、コスト増に
- 突発的な対応が必要:イレギュラーが多く、予定通りに動けない作業は自動化に向かない
- 人間の判断や感情が関わる:クレーム対応、提案文の作成、クリエイティブ作業などは人の力が必要
例えば「クライアントとの商談内容を記録し、最適な提案を考える」ような業務では、データの裏にある意図や感情を読み取る力が求められるため、RPAでは対応できません。
3.2 無理に導入しても効果が出にくいケース
「なんでもRPAで!」と勢いで導入すると、効果が出ないだけでなく、メンテナンスの手間やストレスが増えることも。
特に多い失敗例:
- 月に1回しか使わない作業を自動化 → 自動化コストのほうが費用がかかってしまう。
- ルールが途中で変わる業務をRPA化 → すぐ動かなくなり、修正に追われる。
- 1つの処理に複雑な条件分岐が多すぎる → 開発が難航し、納期が遅れる。
RPAの導入効果は「頻度×単純さ×繰り返し回数」に比例します。逆に言えば、頻度が低くて複雑な仕事には向いていないのです。導入前には、「これはRPA向きの仕事か?」を見極める視点が欠かせません。
3.3 紙ベースの業務をRPA化する場合のAI-OCR連携
紙ベースの業務をRPA化したい場合は、AI-OCR(光学文字認識)技術との連携が必要になります。AI-OCRは紙の文書をデジタル化し、RPAがそのデータを処理できるようにする橋渡し役です。
AI-OCRの精度と留意点
一般的なAI-OCRの認識精度は80~95%程度(文書の品質や書式によって変動)
手書き文字よりも活字の方が認識精度は高い
定型帳票ほど認識精度が上がる傾向にある
AI-OCR導入の追加コスト目安
初期費用:100万円~500万円程度(規模による)
月額費用:5万円~20万円程度
処理量に応じた従量課金の場合もある
AI-OCRとRPAを組み合わせることで、紙の請求書処理や申請書処理など、これまで自動化が難しかった業務も効率化できます。ただし、AI-OCRの認識精度を補うための例外処理の設計も重要です。
4. 業務別に見るRPA導入のビフォーアフター
4.1 経理:請求処理と帳票作成の自動化
経理部門は、「毎月決まった時期に、同じ作業を大量に行う」典型的な部門。中でも請求関連の処理は、RPAとの相性が非常に良く、導入効果も大きい分野です。
RPA導入前の作業の流れ
- 顧客ごとに請求金額を確認
- 請求書をExcelや会計ソフトで作成
- PDFに変換してフォルダに保存
- メールで送信し、送信履歴を記録
RPA導入後
- 顧客データと金額を自動取得
- 請求書を自動作成&PDF化
- 指定の宛先に一斉送信&履歴も自動保存
月末の作業時間が5時間から30分に短縮されたケースもあり、ヒューマンエラーもゼロに。人手不足に悩む企業では「1人分の作業をロボットが担ってくれる」ような感覚です。
4.2 営業事務:見積作成と入力作業の削減
営業担当者が「見積書を作って、システムに登録して、上司に送る」…この一連の作業にもRPAが大活躍。
PRA導入前の作業の流れ
- 顧客からの依頼メールを確認
- 必要情報を転記してExcelで見積作成
- PDF出力&社内システムに入力
- 上長へ報告メールを送信
RPA導入後
- メールをトリガーに自動で見積作成
- 入力ミスゼロの状態で即出力
- 上長報告もテンプレートで自動送信
営業が本来の「売る仕事」に集中できるようになり、営業効率が向上する副次効果も期待できます。「作業」から「商談」への時間配分が変わる、そんな劇的な変化を実感できる場面です。
4.3 総務:社内申請処理の自動化
総務では、交通費申請・備品申請・休暇届などの処理が日々大量に発生します。人が一つ一つ確認して処理していたのでは、作業負担も精神的負荷も大きくなります。
RPA導入前の作業の流れ
- 申請内容をメールやフォームで受領
- 必要な情報を確認し、台帳に転記
- 承認者に転送 → 承認状況を管理
RPA導入後
- 申請を自動でチェック&台帳登録
- 承認者への通知も自動化
- 承認結果に応じた次アクションも自動対応
申請数が多いほど、RPAの恩恵は顕著に現れます。中には「年間で1,000件以上の申請処理が自動化され、1人分の工数を削減できた」という事例もあります。
5. 自社にRPAが合うか?3ステップでチェック!
5.1 自動化対象の見つけ方
「うちの会社でもRPAって使えるのかな?」そんな疑問を解消するために、まずは自動化対象を見つけることが第一歩です。以下のようなチェックリストを使ってみてください。
✓ 毎日または毎週、決まった作業をしている
✓ 複数のシステムやファイルをまたいで転記作業している
✓ 内容はほとんど変わらないのに何度も人が確認している
✓ 作業時間が長い割に付加価値が低いと感じている
これらの項目に3つ以上当てはまる業務があれば、RPAで効果が出る可能性大です。
現場の声を拾って、「地味だけど面倒な作業」をピックアップするのがコツ。現場からの「これ自動でできないの?」という一言が、導入のきっかけになることも。
5.2 効果のざっくり試算方法
自動化候補が見つかったら、次はどれくらい効果が出るかのざっくり試算をしてみましょう。
試算に使うのはこの3つ:
- 1回あたりの作業時間(A)
- 月の実施回数(B)
- 対象人数(C)
効果試算式:A × B × C = 削減時間(1ヶ月)
例えば、1回30分かかる作業を週2回、3人が行っていたとすると:
30分 × 8回 × 3人 = 720分(12時間)/月の削減
これが年間だと144時間。時給1,500円換算なら、21万6,000円分の削減になります。
このように、簡単な式で見える化することで、上司への説得材料にも使えます。
5.3 導入判断の目安とは?
最後に、「本当に導入するべきか?」の判断基準を整理しておきましょう。
以下の3つをクリアしていれば、導入に進んでOKです。
✓ 作業手順が安定していて、ルールが明確
✓ 年間で100時間以上の削減効果が見込める
✓ 既存業務に支障を与えず、徐々に試せる環境がある
逆に、1つでも怪しい場合は「小規模な試験導入」から始めてみるのがオススメ。最初は1業務だけ試して、効果を実感してから社内展開する流れが、最もスムーズです。
5.4 中小企業におけるRPA導入のポイント
RPA導入というと大企業の取り組みというイメージがありますが、実は中小企業こそRPAの恩恵を受けやすい面があります。
中小企業におけるRPA導入のメリット
- 少人数でも大きな効果:一人何役もこなしている環境では、定型作業の自動化効果が顕著
- 導入判断が早い:意思決定のスピードが速く、小回りが利くので試行錯誤がしやすい
- クラウド型RPAの活用:初期投資を抑えたクラウドサービスの活用で、コスト面のハードルが下がった
中小企業での導入ポイント
- まずは小さく始める:全社展開より、最も効果が見込める1業務から着手する
- 社内の理解促進:「ロボットに仕事を奪われる」という不安を払拭し、「単純作業から解放される」という利点を伝える
- 外部サポートの活用:RPA導入の経験がある外部パートナーの力を借りる
- 補助金の活用:IT導入補助金など、中小企業向けの各種支援制度を活用する
6. まとめ:RPA導入は業務選びが9割
RPAを導入する目的はただひとつ。「人の手間を減らし、仕事をもっと楽にすること」です。
ですが、RPAがすべての業務に効くわけではありません。今回ご紹介したように、導入効果は「どの仕事に使うか」によって天と地ほどの差が出ます。
実際、請求書処理やデータ転記のように劇的な時短になる業務もあれば、判断が必要だったり、ルールが曖昧な業務では全く効果が出ないケースもあります。だからこそ、RPA導入の成否は「業務の選び方」で9割決まるのです。
まずは社内を見渡して、「この作業、毎回同じで無駄じゃない?」「これって人がやらなくてもいいのでは?」そんな業務をピックアップしてみてください。
そこからが、あなたの会社にとって最も価値のあるRPA導入のスタート地点になります。
関連ページ
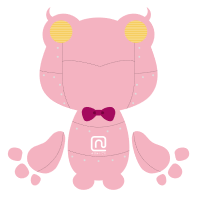
ネットリンクスではRPAの導入からシナリオ作成、運用までしっかりとサポートいたします。
初めての方でも安心して導入できるよう、セミナーや個別相談もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
岡山・香川のDXなら「おったまのDX研究所」におまかせ!
導入前のご相談から導入後のフォローまで手厚く対応いたします。
ご相談はお気軽にどうぞ!